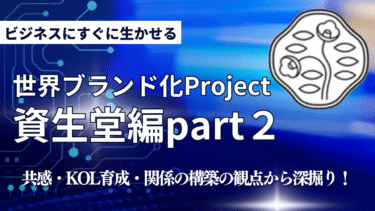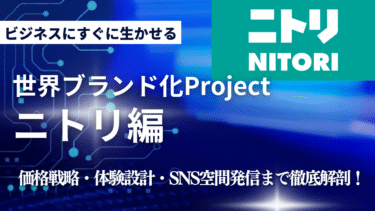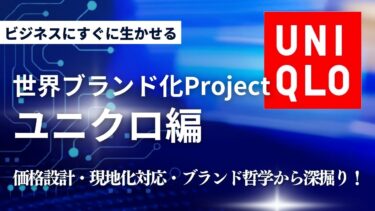“地方発ラーメン店”が世界で勝てたローカル戦略とは
こんにちは。
今回は、熊本発のラーメンチェーン「味千ラーメン」が、なぜ中国市場で600店舗を超えるまで拡大できたのかを解説します。
キーワードは「派手な広告」でも「グローバル基準」でもありません。
その本質は、現地文化と寄り添う“ローカル共創型戦略”にありました。
きっかけは“1人の中国人留学生の声”
味千ラーメンの海外展開は、1994年に1人の中国人留学生が
「本格的な豚骨ラーメンを中国でも食べたい」と言った一言から始まりました。
1号店をオープンするも、当初は「ラーメンは脂っこすぎる」と苦戦します。
ここで取った戦略は、無理に合わせるでも、押し付けるでもない方法でした。
「味を守りながら、生活に合わせる」
味千ラーメンは、文化に寄り添うかたちで柔軟に調整しました。
ラーメン単品ではなく、ご飯とセットにした“定食化”
ニンニクや油の調整、辛味のトッピング自由化
昼はランチ、夜は居酒屋スタイルに分けて提供
このように、味のコアを守りながら“食べ方”をローカライズしたことが、現地に自然に溶け込むカギとなりました。
一律展開ではなく、地域対応が成功の鍵
中国は都市によって、味の好み・食事の時間・購買動機が大きく異なります。
そこで味千は:
地域ごとにフランチャイズオーナー制度を採用
現地裁量でメニュー開発・食材仕入れが可能
“地元のラーメン屋”としての顔を育てる
この柔軟な運営方針により、日本ブランドでありながら、現地密着型チェーンとして定着していきました。
ストーリーの共有が“信頼”を生んだ
味千ラーメンは、ただ味で勝負するのではなく、創業者の思い・職人文化・熊本発の背景といった「物語」も丁寧に発信していきました。
店内POPで創業ストーリーを紹介
SNSや映像で“安心・ぬくもり”を表現
ブランド名も「味千=家族のようなあたたかさ」と再解釈される
ブランドとは“文化の翻訳”。
こうした取り組みで、価格や機能では得られない“心の価値”が生まれたのです。
中小企業でも活かせる!味千に学ぶ3つの戦略視点
文化に違和感なく溶け込む視点を持つ
→ 売れない理由を“文化の壁”として分析し、調和する形で届ける。地域ごとの最適化で“自分ごと化”される
→ 現場の裁量を活かせば、顧客が“自分の街の店”と感じるようになる。創業ストーリーが“価格競争を超える武器”になる
→ なぜこの商品を出すのか?を語ることで、模倣されない差別化に。
世界ブランド=グローバル基準ではない
味千ラーメンが証明したのは、「地域に根ざす」ことこそが最強のブランディングであるという事実です。
地元に愛されるブランドづくりは、海外市場でも圧倒的な信頼を生みます。
海外で“自社らしく売りたい”企業へ
私たちは、御社の商品やサービスが“現地で自然に伝わる”ための戦略設計をサポートしています。
無理に合わせず、らしさを守りながら文化に融合する。
そのための市場調査・戦略設計・SNS活用など、トータルでご相談いただけます。
次回は、ニトリが中国で“コスパの象徴”として定着したブランディング戦略を解説します!
あわせて読みたい
・無印良品が“空間”で思想を伝えた中国戦略
・資生堂がKOL戦略でZ世代に刺さった理由
・ニトリが“真似したくなる暮らし”をSNSで拡散させた戦略