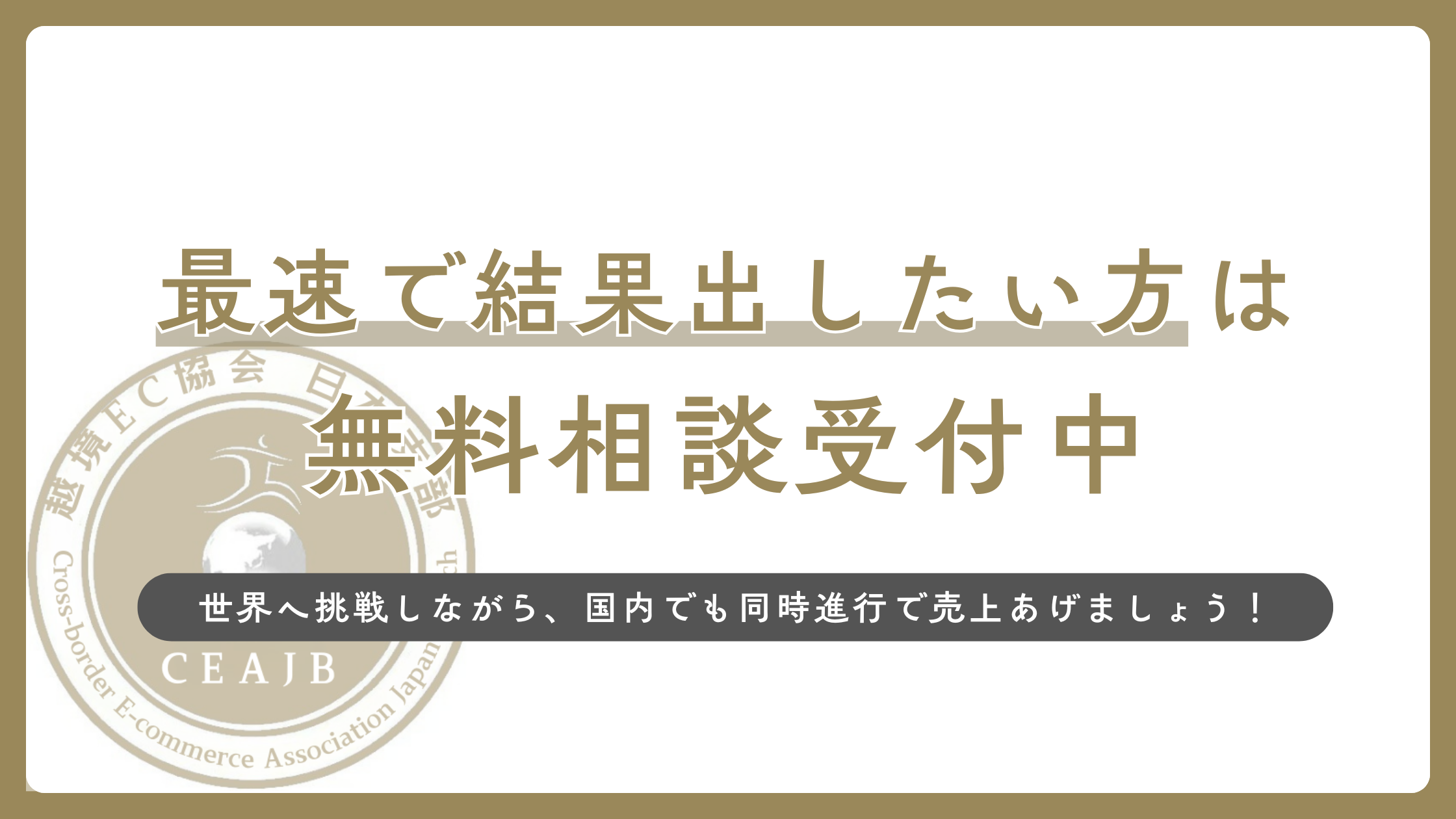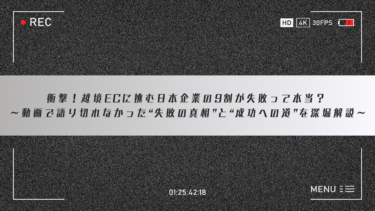4-1 知的財産権や商標権の保護
越境ECを展開する際、真っ先に考慮すべきなのが知的財産権や商標権の保護です。
たとえば、日本では登録済みのロゴや商品名が、海外ではすでに他社に商標登録されていることもあり、販売差し止めや訴訟のリスクがあります。
中国市場では特に注意が必要で、「先取り商標」問題が多発しています。
ある日本の健康食品メーカーは、中国進出前に現地企業に商標を先に登録され、製品名を変更せざるを得ませんでした。
事前に中国商標局サイトで類似商標を調査し、弁理士や現地代理人を通じて速やかに出願・登録しておくべきです。
さらに、日本国内で商標登録済みでも、海外での効力は及ばないことを認識し
主要ターゲット国(特に中国・米国・EU)での個別登録が推奨されます。
国際登録制度(マドリッド・プロトコル)も活用することで、効率的に権利保護が可能です。
4-2 関税と税金に関する知識
国をまたぐ取引では、関税や消費税(VAT)、輸入税などが発生します。
これらの税率や制度は国ごとに異なり、適切な情報収集と申告が不可欠です。
たとえば、EU圏では2021年からすべての越境取引にVATが課税されるようになり
IOSS(Import One-Stop Shop)を通じて取引金額に応じたVAT納税が求められます。
IOSS番号を取得し、各国ごとの税務処理を一元化することで、通関時のトラブルを回避できます。
一方、中国市場では、越境EC企業向けに「中国越境EC総合試験区」制度が整備されており
特定のプラットフォーム(Tmall GlobalやJD Worldwideなど)を通じて取引する場合、関税が簡素化・軽減されるケースがあります。
また、中国政府が指定する「正規越境EC商品リスト」に掲載されている商品は
特別な通関ルートと税率が適用されるため、対象商品を選定する戦略が有効です。
4-3 プライバシー保護規制(GDPRなど)への対応
越境ECでは、ユーザーの個人情報を扱うため、各国のプライバシー保護規制に対応する必要があります。
特にEUのGDPR(一般データ保護規則)は世界的にも厳格で、違反時には高額な罰金が科される可能性があります。
たとえば、EUユーザー向けサイトには「Cookieバナー」の設置と、利用目的別の同意取得が必須です。
さらに、情報提供・削除依頼に応じる体制も整える必要があります。
日本国内の中小企業でも、GDPR準拠のECサイト構築サービスを活用すれば、比較的低コストで対策が可能です。
また、中国でも2021年から「個人情報保護法(PIPL)」が施行され
ユーザー情報を収集・利用する際には、明確な同意取得とデータ管理体制の整備が義務付けられています。
現地パートナーと協力して対応することが重要です。
4-4 各国の文化や商習慣を考慮した運営
文化や商習慣の違いを理解し、それに合わせた運営が越境EC成功の鍵です。
例えば、中国では「チャットで安心してから購入する」文化が根強く
ライブチャット機能やWeChat公式アカウントでの対応が重要です。
また、「縁起が良い色(赤や金)」のパッケージや、「八」「六」といった好まれる数字を活用した価格設定も
購入意欲を後押しする要素になります。
アメリカではスピード重視の文化から、配送日数の明確表示や返品のしやすさが重視される傾向があります。
一方、ドイツなどのヨーロッパ諸国では「商品の詳細説明」「安全性への配慮」「環境配慮への明示」が重視されるため
商品ページの設計も調整が必要です。
4-5 支払い方法の選択とセキュリティ対策
各国のユーザーが慣れ親しんでいる支払い方法を用意することは、コンバージョン率に直結します。
たとえば、中国ではAlipayやWeChat Payが主流であり、これらが使えないと購入を諦めるユーザーも少なくありません。
また、タイではPromptPay、ドイツではKlarna、日本ではコンビニ払いなど、地域ごとに主流となる決済手段は異なります。
ターゲット市場の決済事情を調査し、それに応じた対応が必要です。
セキュリティ対策としては、3Dセキュア、SSL暗号化通信、トークン化決済の導入が求められます。
不正利用対策にはAIを用いた検知ツールの導入も効果的で、決済代行業者との連携によるリスク軽減も検討しましょう。
4-6 言語の壁を乗り越えるための翻訳ツール活用
多言語対応は越境ECの基本ですが、限られた予算やリソースの中で効率的に対応するには翻訳ツールの活用が有効です。
Google翻訳やDeepLは、初期段階の翻訳やリアルタイム対応に便利ですが
製品説明やマーケティングメッセージには不自然な表現も混在することがあります。
そのため、クラウドソーシングサービス(Gengo、Conyacなど)を活用し、ネイティブチェックを依頼することで品質を担保できます。
さらに、ShopifyやWixなどのECプラットフォームには
多言語対応機能が標準搭載されており、手軽に導入できます。
商品レビューやカスタマーサポートへの自動翻訳機能も併用すれば、言語の壁を大きく下げることができます。
4-7 越境ECで起こりやすいトラブルとその回避法
越境ECでは、配送遅延、関税トラブル、商品破損、返品対応など、国内ECとは異なる問題が発生しやすいです。
たとえば、中国宛の配送では、HSコードやインボイスの不備、送付先住所の簡体字未対応などが原因で税関での足止めや返送が多発します。
これを防ぐには、越境EC専門の物流パートナー(佐川グローバル、ヤマト国際便、4PXなど)と連携し
必要書類の自動生成や現地語住所変換ツールを活用することが効果的です。
また、返品ポリシーが曖昧だと、クレームや返金トラブルにつながります。
たとえば、アメリカでは「理由を問わず返品可」が常識なため、「未使用・30日以内であれば返品可能(送料は購入者負担)」といったルールを事前に明記し
FAQや返品フォームでスムーズな対応を行うことが求められます。
トラブル時の社内対応マニュアルやテンプレート文面をあらかじめ用意しておけば、対応品質を均一化でき、顧客満足度の向上にもつながります。